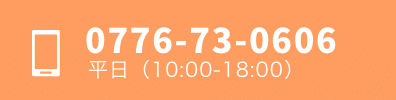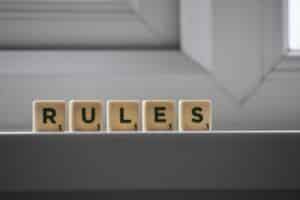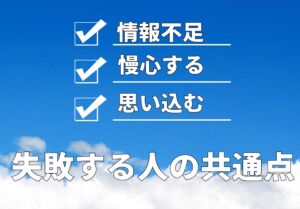「ODMとOEMは何が違うの?」
「どちらを選んだらいいの?」
「OBMやEMS、PBとの違いは?」
こういった疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
メーカーが販売している商品には、自社で製造したもののほかに、「ODM」「OEM」という方法で生産されたものがあります。
ODMとOEMはアルファベットが似ているということもあり、違いがわかりにくいですよね。
そこで今回は、ODMとOEMの概要とそれぞれのメリット・デメリットを解説いたします。
事業に適した生産方法を選ぶポイントも紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
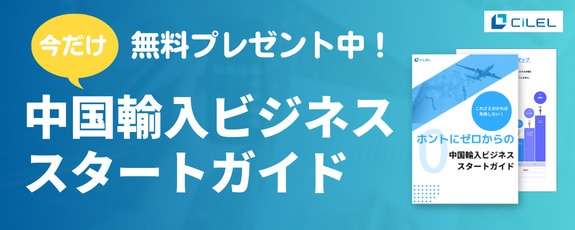
目次
ToggleODMとOEMの違いとは?
ODMとOEM。
響きはとても似ていますが、その内容は少し異なります。
この章では、それぞれの概要を紹介したうえで、ODMとOEMの違いを解説していきます。
ODMとは
ODM(Original Design Manufacturing)は、製品の設計から生産までを委託することを指します。
ODMとは、Original Design Manufacturingの略語で、委託者のブランドで製品を設計・生産することをいいます。
たとえば、アパレルブランドA社が、ODM製造業者Bに商品生産を発注したとしましょう。
ODM製造業者Bは、製品の設計や開発・製造・生産を請け負います。
完成した商品は、発注元であるアパレルブランドA社で販売します。
これがODM生産です。
ODMとは、設計から生産までの工程を外部委託する生産方法のこと
受託者(ODM製造業者)の中には、マーケティング・物流・販売まで自社で引き受け、複数のブランドの製品を一貫して提供するところもあります。
企業や契約によって、それぞれ担当する業務の幅が異なる点がポイントです。
近年、ODMは台湾や中国の企業に多くみられ、パソコンや携帯電話などの業界において盛んに活用されています。
OEMとは
OEM(Original Equipment Manufacturing)は、製品の生産を委託することを指します。
たとえば、自動車メーカーC社が、製造業者DにOEM生産の依頼をしたとしましょう。
製造業者Dの工場やメーカーでは、各工程の中の「製造」部分を請け負います。
商品の企画や開発・設計・販売は、自動車メーカーC社が自社でおこないます。
これがOEM生産です。
OEMとは、製造工程を外部委託する生産方法のこと
OEMは一般的に、技術や販売における企業間の提携や、経営効率を上げることを目的に活用されています。
専門性の高い依頼の場合、委託者側が技術的な指導をおこなったり、反対に同水準の技術を持つライバル企業同士がOEMを採用し合ったりするケースもあるようです。
OEMもさまざまな業界で活用されていますが、とくに以下の生産業界では定番の手法として定着しつつあります。
【OEMがよく利用されている商品ジャンル】
・自動車
・家電
・アパレル、ファッション小物
・スポーツ、アウトドア用品
・生活雑貨 など
OEMのメリットについては『OEMのメリット・デメリットとは?』の記事内で詳しくご紹介しています。
ぜひ参考にしてください。
ODMとOEMの違いは「受託者が担う範囲」
ODM生産とOEM生産の違いを表にまとめました。
| ODM生産 | OEM生産 | |
| 違い | ・設計から生産まですべて受託者が請け負う ・受託者の技術レベルの水準が高い傾向 ・委託者と受託者は対等な関係にある場合が多い |
・製造工程のみ受託者が請け負う ・委託者(発注者側)が技術指導をおこなうケースもある ・委託者が主体になるパターンが多い |
ODMとOEMの違いは、受託者が担う範囲です。
ODMでは、製品の設計や開発・生産に至るまで、すべて受託者が請け負います。
場合によっては、マーケティングや物流・販売まで引き受けるケースもあるようです。
そのため、ODMの受託者の技術レベルは高い水準であることが多いといわれています。
一方OEMでは、製品の設計や開発などは、すべて委託者(発注者側)がおこないます。
受託者は、製造のみを担当。
届けられた設計書や図面に従って製造するため、委託者側が技術指導をおこなうケースもあるようです。
工程のどこまでを外部に委託するかによって、ODMかOEMかが変わってくるといえますね。
とはいえ、近年は産業のグローバル化に伴い、生産方式も多様化。
製造をおこなわないODM企業もあれば、設計も請け負うOEM企業も存在しており、ODMとOEMの違いが曖昧になってきています。
ODMとOEMのメリットの違い
ODMとOEMは、メリットにおいてどのような違いがあるのでしょうか。
委託者・受託者それぞれの観点から、わかりやすく解説していきます。
ODM委託者のメリット
ODMの委託者のメリットは、おもに以下の4つです。
【ODM委託者】
・設計や開発のノウハウがなくても商品を作れる
・技術の取得や生産に関するコストを削減できる
・在庫リスクが少ない
・販売やアフターサービスに専念できる
ODM委託者の最大のメリットは、専門知識がなくても商品を作れるところでしょう。
商品生産までの工程を一貫して受託者に任せるので、開発などの専門的ノウハウや、商品についての知識がない状態であっても依頼できます。
委託者側でおこなう工程がほとんどないため、販売やアフターサービスに専念できる点も魅力ですね。
ODMの受託者のメリット
一方ODMの受託者のメリットには、次の2点が挙げられます。
【ODM受託者】
・高い技術力による利益が得られる
・生産量が増え収益が上がる
ODM受託者は、空いた時間や製造設備を活かして商品を生産できるため、収益を伸ばせるなどのメリットがあります。
依頼数が増えれば増えるほど、技術レベルも向上。
信頼を得られる機会にもなりますね。
自社ブランドを構築しなくても利益につながりやすいのは、利点といえるでしょう。
OEM委託者のメリット
OEMの委託者には、以下4つのメリットがあります。
【OEM委託者】
・生産能力の不足をカバーできる
・生産コストを削減できる
・在庫リスクが少ない
・新商品の開発や販売に専念できる
OEM委託の特徴的なメリットは、重要な要素をコントロールできる点です。
設計や企画、スケジュールといった、「生産以外」の重要部分は自社でおこなうため、調整しやすいですね。
製造のみ任せるため、コスト削減にもつながります。
OEM受託者のメリット
続いてOEMの受託者のメリットを見ていきましょう。
OEM受託者のメリットは次のとおりです。
【OEM受託者】
・委託者からの指導や経験により技術力が向上する
・生産量が増え収益が上がる
専門性の高いOEMの依頼を受けた場合、委託者が受託者に技術的な指導をおこなうケースがあります。
適切な指導を受けることで、受託者の技術力の向上が見込めます。
くわえて、ODMに比べてローリスクです。
工程を一貫しておこなうのではなく、委託者の指示に従い製造するため、安心して受託できるといえるでしょう。
ODMとOEMのデメリットの違い
ODMとOEM、どちらもメリットが多いですが、デメリットもあります。
委託者・受託者別に紹介していきます。
ODM委託者のデメリット
ODMは委託者にとって、以下4つのデメリットがあります。
【ODM委託者】
・自社の設計・開発・生産技術が育たない
・委託先が競合になるリスクがある
・委託する工程が多いため販売価格が上がってしまう
・自社と似た商品が出回ってしまう
ODMでは、OEMに比べて多くの工程を他社に委託することになります。
一連の流れを請け負ってもらうと、手間や時間の負担は軽減しますが、自社での設計や開発の技術は育ちません。
また、将来委託先(受託者)が同業の競合になってしまう可能性も考えられますね。
委託する工程が多い分、商品一つあたりの生産コストが高くなってしまうデメリットもあります。
ODM受託者のデメリット
一方、ODMの受託には、次のようなデメリットがあります。
【ODM受託者】
・生産ノウハウが流出する可能性がある
・引き受ける工程が多い分リスクが高くなる
・自社ブランドが浸透しにくい
受託者の技術レベルが委託者よりも高い水準にあることが多いODMは、他社とのやり取りの中で自社のノウハウが流出してしまう可能性があります。
また、引き受ける工程が多い分、コストや品質などにおける自社のリスクが高くなるといったリスクもあります。
OEM委託者のデメリット
OEMの委託者のデメリットは、次のとおりです。
【OEM委託者】
・自社の生産技術が育たない
・委託先が競合になるリスクがある
・自社生産による収益が得られない
OEMも、生産(製造)を外部に委託するため、ODMと同様生産に関する技術が育ちにくいデメリットがあります。
また近年は、OEMを専業としていた製造元がスキルを活かして独立し、同じ業界で自社ブランドを立ち上げるケースが多くみられます。
とくに競争が激しい業界では、将来的に委託先が競合になるリスクを考慮する必要があるでしょう。
OEM受託者のデメリット
一方、OEMを受託する場合、以下2つのデメリットがあります。
【OEM受託者】
・生産ノウハウが流出する可能性がある
・自社ブランドが浸透しにくい
OEMではODMと同様に、他社とやり取りを繰り返すうち、生産ノウハウが流出する可能性があります。
また、他社ブランドの名前で商品を生産するため、自社ブランドが浸透しにくいリスクもあります。
事例から見るODMとOEMの違い
「具体例を知りたい」と感じている方もいるのではないでしょうか。
次に、実際にODM・OEM生産されている商品の事例を紹介します。
ODM生産の例
ODMは、スマートフォンやパソコン業界でよく活用されています。
【ODM生産されている製品例】
・大手スマートフォン
・パソコン本体
・入退室カードリーダー
・オリジナルステーショナリー など
たとえば、NTT docomoのスマートフォンは、SONYやNEC、富士通などのメーカーが開発・設計・製造を担当。
完成した製品は「NTT docomo」のブランドのもと、販売されています。
また、水族館や動物園、花鳥園などで販売されている「オリジナルグッズ」もODM生産のひとつです。
靴下や封筒、ハンカチやメモ帳など、そこでしか買えない商品がたくさん並んでいるのを見たことがある方も多いのではないでしょうか。
近年は、委託者が依頼する方法のほか、受託者が委託者に設計や企画を提供し、ODMをオファーするケースもあります。
アパレル業界でのODM生産について解説した記事もあわせてご覧ください。
『アパレルにおけるODM生産の特徴とは?』
OEM生産の例
OEM生産は、自動車や化粧品、家電業界などで広く活用されています。
以下、例を挙げてみましょう。
【OEM生産されている製品例】
・トヨタ「ルーミー」
・iPhone
・ダイキン「ガスヒートポンプエアコン室外機」 など
たとえば、トヨタ自動車で販売されている「パッソ」は、軽自動車メーカーである「ダイハツ」で製造されています。
同じように、トヨタ車「ルーミー」のベースは、ダイハツの「トール」。
ルーミーは、トールのOEM車といえます。
OEMの種類や具体的な商品例、流れについては、下記の記事で紹介しています。
『OEM品にはどんなものがある?』
簡易OEMについて
アパレル商品や雑貨商品を中国から仕入れる場合など、「簡易OEM」という言葉が使われることがあります。
「簡易OEM」は形態としてはODMに近く、すでに存在する製品にオリジナルのタグだけつけたり、ネームだけつけたりする方法です。
中国輸入の簡易OEMについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。
『中国輸入で簡易OEM!アパレル商品のタグを付け替えて自社ブランドとして販売』
『中国輸入OEMでオリジナル商品をつくる手順は?事例や注意点も解説!』
ODM?OEM?選ぶ際の3つのポイント
ここでは、ODM生産かOEM生産かで迷ったときの選定ポイントを3つご紹介いたします。
・コスト
・品質
・運用期間
ポイント①コスト
ポイント1つめは「コスト」です。
一般的に、生産コストには材料費や人件費、道具や製造設備の導入費などが含まれます。
製造に関しては、ODMとOEMともに他社に委託するため、生産コストの大きな違いはありません。
しかし、ODMでは設計や開発、場合によってはマーケティング・物流・販売まで他社に委託します。
もし、自社でノウハウが不足している状態、かつ高度な商品を開発する場合は、ODMを利用した方が低コストになる可能性が高いでしょう。
反対に、自社内である程度ノウハウがある場合は、OEMを活用した方が委託にかかるコストを最低限に抑えることができます。
ポイント②品質
ポイント2つめは、「品質」です。
ODMでは、より多くの工程を他社に委託します。
したがって、細かい作業や流れの把握が難しく、品質は受託者の技術レベルにより左右されてしまいます。
品質を担保するには、ODMメーカー選びが重要になってくるといえますね。
一方OEMでは、設計や開発は委託者側がおこなうため、ある程度の品質は事前に確保することができます。
OEM生産の場合、品質に不安がある場合は、早めの段階で綿密なコミュニケーションを取り、希望を正確に伝えるよう意識しましょう。
ポイント③運用期間
ポイントの3つめは、「運用期間」です。
長期的に運用するかどうかで検討します。
ODMかOEMかを選ぶ際には、事業の方向性に合っているかなど、長期的な視点で見極めることが重要になります。
たとえば、長期に渡りODM生産を依頼するとしましょう。
長期でODM生産を委託すると、受託側では技術や知識が蓄積されていきますが、委託側が同様の技術レベルに達するのは困難です。
結果、受託者を頼らなければ製品を製造するのが難しくなってしまう可能性があります。
また、長期的な委託によって社外にノウハウが流出し、受託者が同業の競合になってしまうケースもあり得ますね。
OEMであれば、自社で技術を高めながらの運用が可能です。
とはいえ、ノウハウの流出のリスクがある点などは、ODMと変わりません。
ODMとOEM、両者の特徴を考慮しながら、事業の方向性に沿った方法を選択しましょう。
OBM・EMS・PBとの違い
ODMやOEMの他にも、生産に関する以下のような方式があります。
・OBM
・EMS
・PB
この章では、それぞれの方式の特徴、ODMやOEMとの違いを解説していきます。
OBMとは
OBMとは、Original Brand Manufacturingの略称。
自社のオリジナルブランドの商品を、自社で生産する方式のことです。
かつてOEMで他社ブランドの商品を生産していた製造元が、ODM事業を展開し、最終的にOBMに成長した際に用いられます。
性質的にODMやOEMと対照的だと思われることが多いですが、実はこの2つの延長線上にあるのがOBMなのです。
EMSとは
EMSとは、Electronics Manufacturing Serviceの略称。
文字通り電子機器の生産を受託するサービスを指します。
1980年頃のアメリカで広まったこの方式は、現在、電子機器メーカーによって主に台湾などで採用されています。
EMSではODMの形態をとる場合とOEMの形態をとる場合があり、どの工程までを他社に委託するかは企業によって異なります。
PBとは
PBとは、Private Brandの略称。
スーパー、コンビニ、ドラッグストア、家電量販店などの小売業が企画したプライベートブランドの商品を、他社が生産することを指します。
生産のみ他社に委託するという意味ではOEMと似ていますが、OEMとPBの主な違いは、委託者が誰かという点です。
【OEMとPBの違い】
OEM:メーカーがメーカーに製造を依頼する
PB:小売店やサービス業者などがメーカーに製造を依頼する
また、小売業が企画したプライベートブランドの商品自体をPBと呼ぶこともあります。
委託側によって呼び方が異なりますが、OEMとPBは実質的には同じものと考えていいでしょう。
中国輸入でOEMをするには?
OEMでオリジナル商品を製造する際に、よく検討されているのが中国輸入です。
中国輸入でOEMをおこなう理由としては、商品の仕入れやすさや、製造メーカー側にOEM生産の知識・経験があること、などが挙げられます。
「中国でのOEM」というと、大きな企業がおこなうイメージがあるかもしれませんが、実は輸入代行業者を利用すれば事業規模がさほど大きくなくてもOEM生産をおこなうことができます。
CiLEL(シーレル)は2011年より中国仕入れ代行サービスをご提供しておりますが、CiLELのお客様には、OEMにチャレンジするタイミングの目安として「年商1,000万円を超えた頃」とお伝えしています。
輸入代行業者を利用する中国輸入OEMでは、輸入代行業者が中国側の工場とやりとりをしてくれるため、中国工場とのつながりがない場合やコミュニケーションに不安がある場合は輸入代行業者を利用するのもひとつの方法です。
こちらの記事も参考にしてください。
『【中国輸入OEM完全ガイド】代行業者おすすめ3選も紹介』
ODMとOEMの違いを理解して戦略を立てよう
いかがでしたでしょうか。
最後に、ODMとOEMの特徴と違いについてまとめます。
ODMとは、Original Design Manufacturingの略語で、受託者が他社のブランドの商品として製品を設計・生産することを指します。
一方OEMは、Original Equipment Manufacturingの略語で、受託者が他社のブランドの商品として製品を生産することを指します。
ODMとOEMの違いは大きく分けて3つあります。
・受託者が担う範囲
・委託者と受託者の技術レベルの差
・委託者と受託者の関係
ODMとOEMで最も大きな違いは、受託者がどの工程までを引き受けるかです。
それぞれにメリットとデメリットがありますが、ODMかOEMで生産方式を迷っている場合は、以下の3つのポイントを意識してみましょう。
・コスト
・品質
・運用期間
また、ODMやOEM以外の生産方式として、以下の3つが挙げられます。
・OBM
・EMS
・PB
長期的な視点で事業の方向性と合うかどうか吟味しながら、最適な戦略を立てていきましょう。
投稿者プロフィール

- CiLEL編集部
-
『中国仕入れをもっと簡単に。』
中国からの輸入仕入れ代行サービスCiLEL(シーレル)を運営しています。
中国輸入の基礎知識ブログでは、海外仕入れやEC事業を行う事業者様に役立つ情報を発信中です!